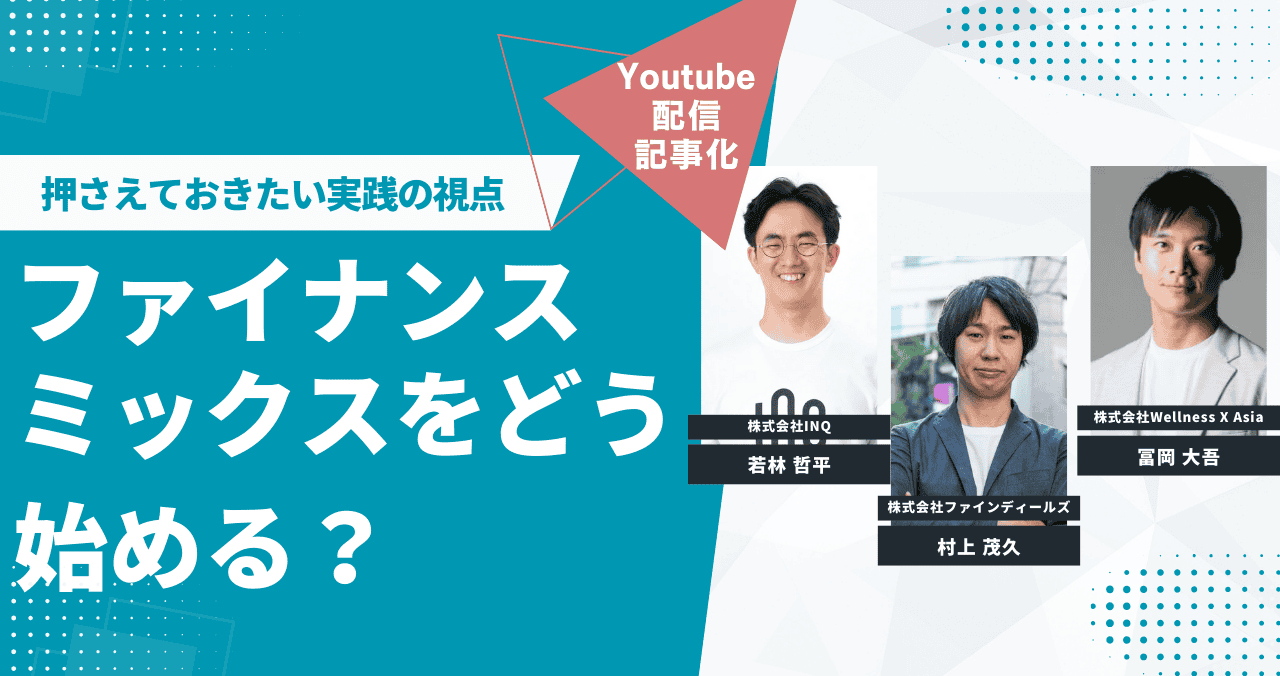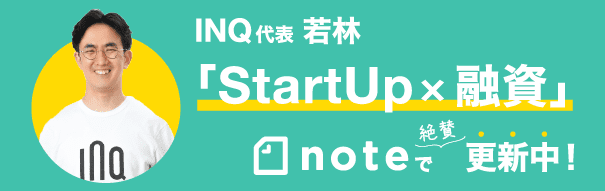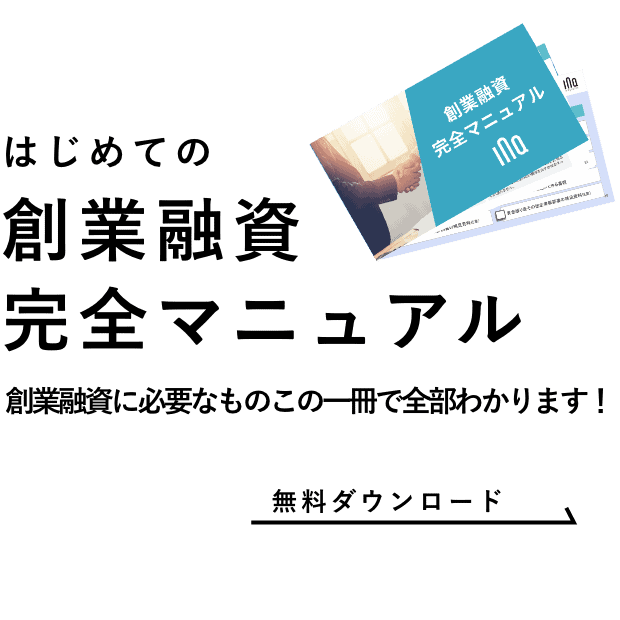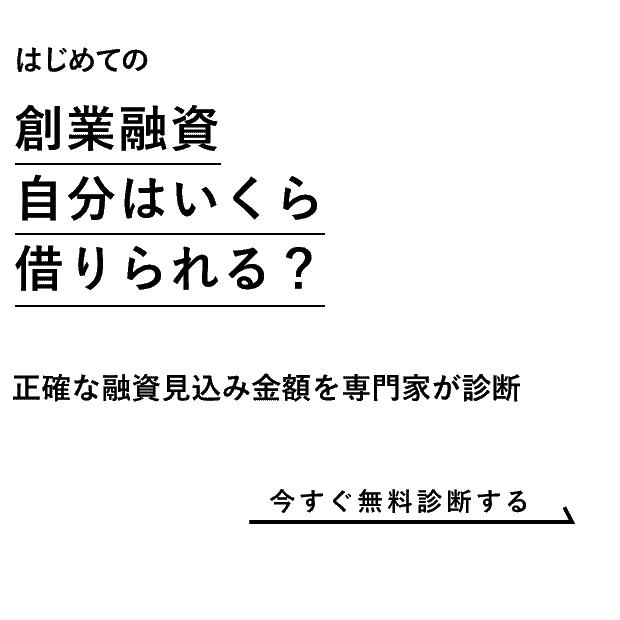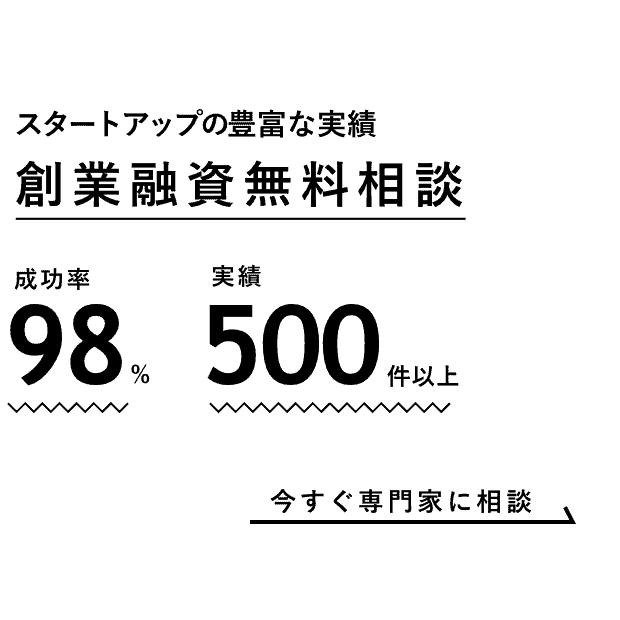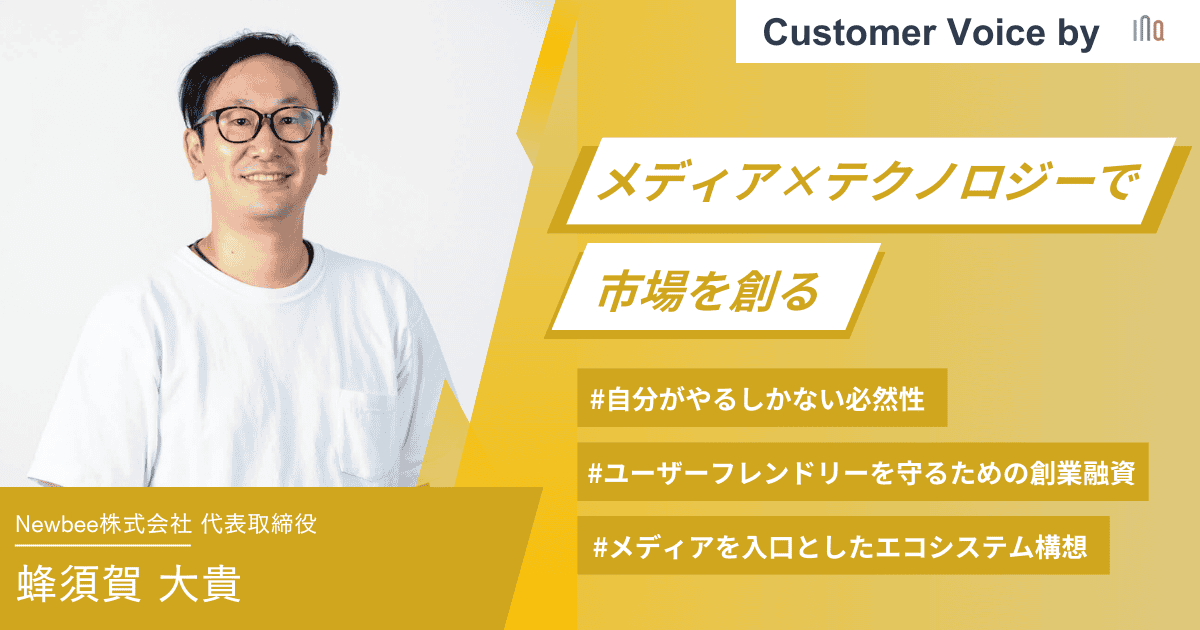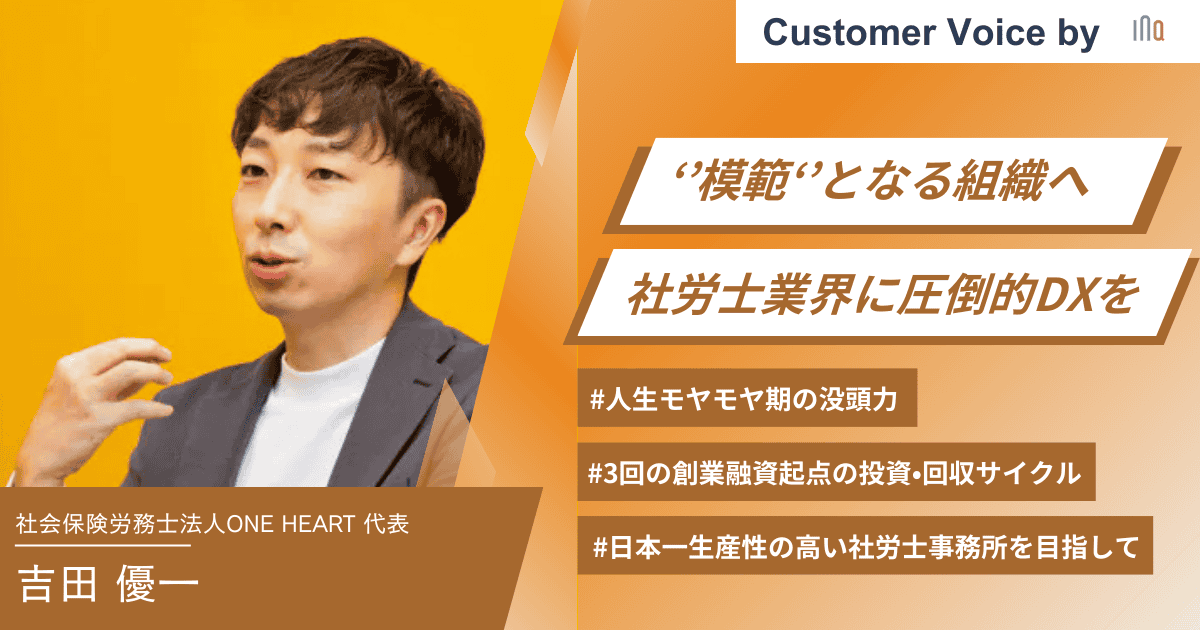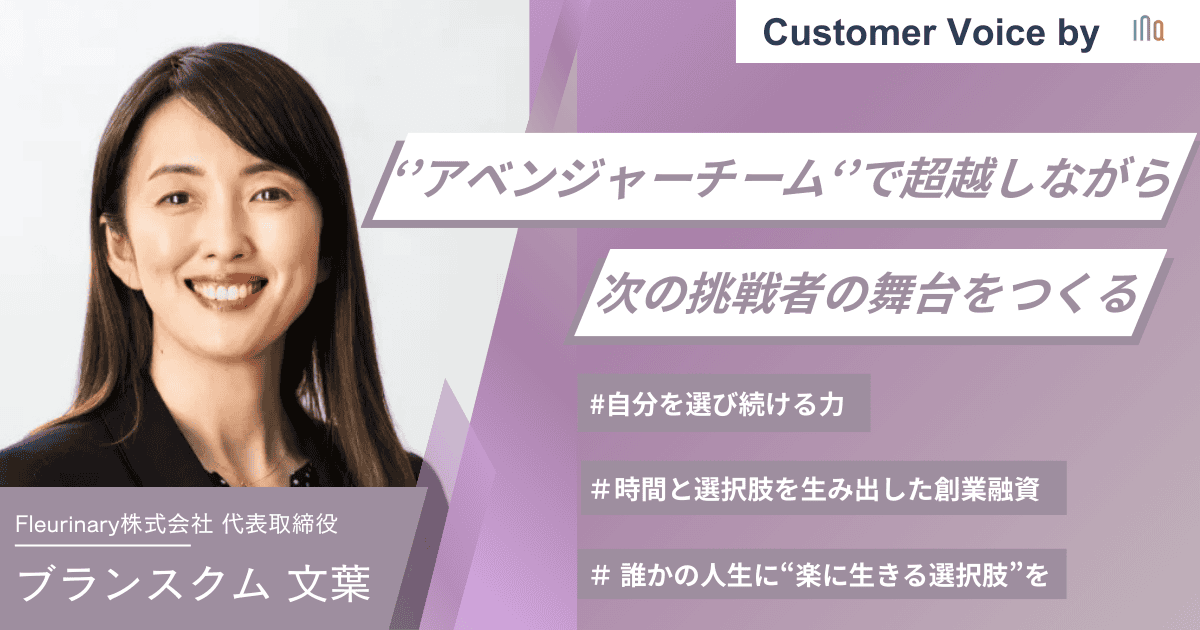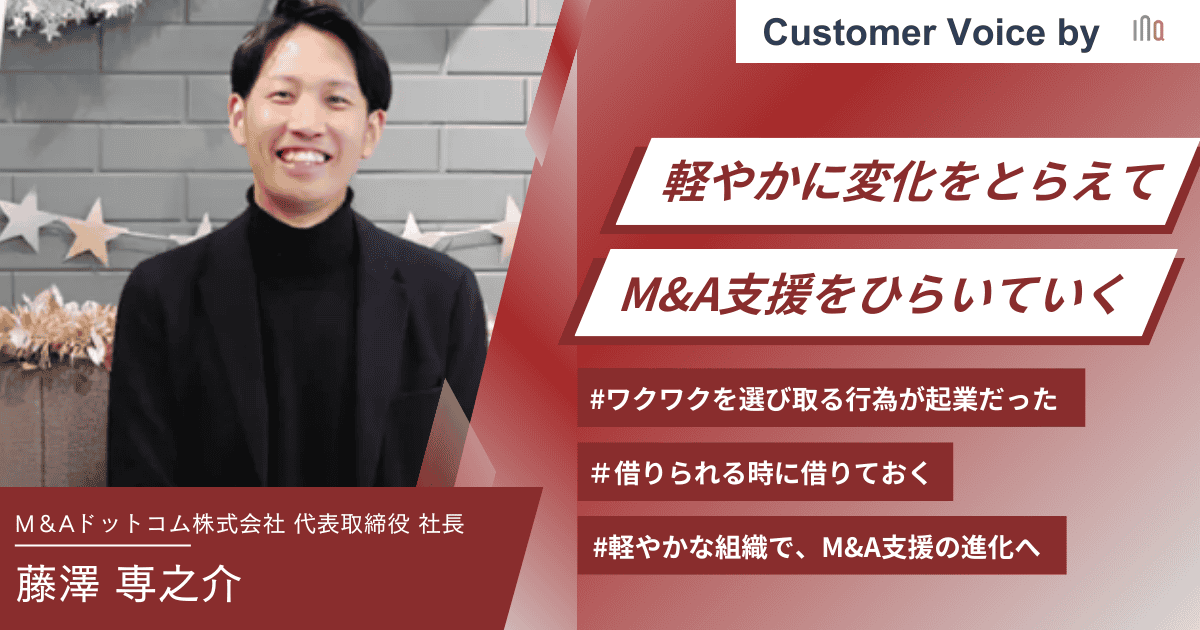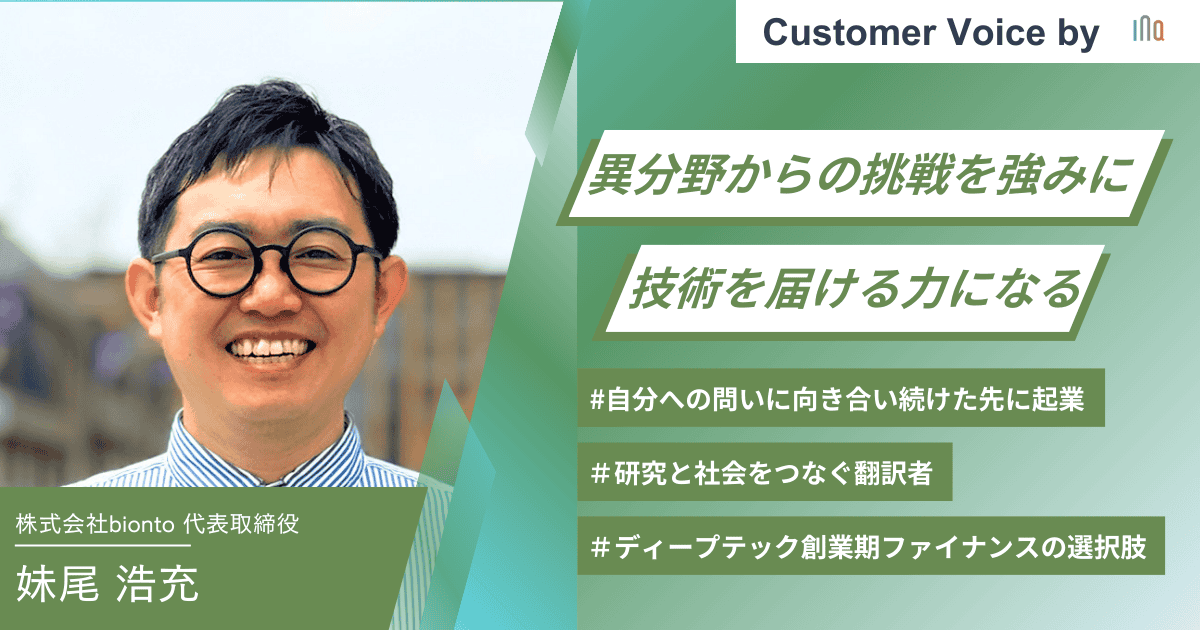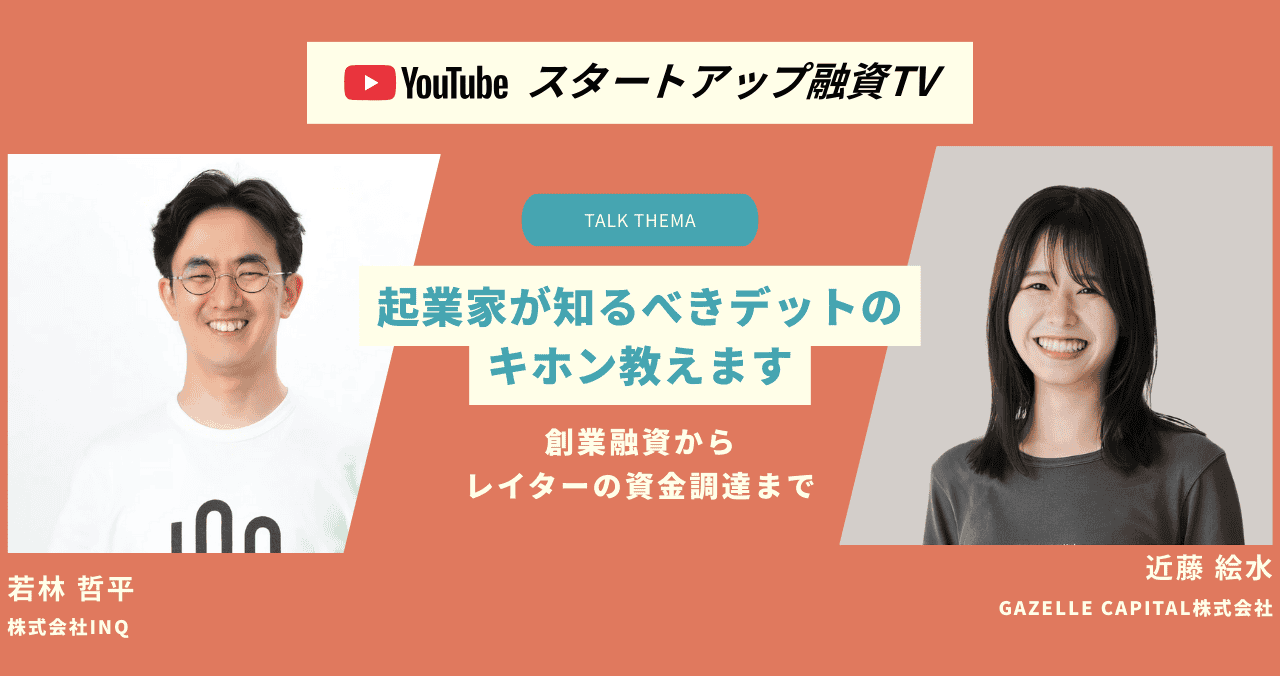若林 哲平
最新記事 by 若林 哲平 (全て見る)
- 【融資相談室】知らないと損!無担保・無保証の「女性・若者・シニア創業サポート事業2.0」を徹底解説 - 2025年12月12日
- 【M&Aバンク】押さえておきたい実践の視点|ファイナンスミックスをどう始める? - 2025年9月30日
- 【融資相談室】日本政策金融公庫 資本性ローンで5000万円を掴む!融資のプロが語る「攻めの調達戦略」 - 2025年9月25日
スタートアップの資金調達といえば、長らくベンチャーキャピタル(VC)からの出資が主流でした。しかし、市場環境の変化や企業体としての描く多様な未来などを背景に、その常識は変わりつつあります。様々なファイナンス手段を戦略的に組み合わせ、成長資金を確保する「ファイナンスミックス」は、市場の中で持続的に社会への価値提供を目指す事業者のファイナンスの視点として、押さえておきたい土台となる概念といえます。
- なぜ今、ファイナンスミックスが注目されているのか?
- ファイナンスミックスを検討する上で、まず何からはじめたらよいのか?
株式会社WXAコンサルティングの冨岡さんがMCを務めるM&A特化Youtube番組『M&A BANK』で、『60分でわかる!ファイナンス超入門』共著者の村上さんと共に解説した回の内容を基に実践的なガイドとしてご参考ください。
本記事は、M&A特化Youtube番組『M&A BANK』に出演させていただいた「M&Aを目指す経営者も知っておくべきファイナンスミックス【資金調達】|Vol.1210」以下の回を基に、実践的なガイドとして再編集したものです。
キーワードは「ファイナンスミックス」―なぜ今、注目されるのか?
冨岡:最近のスタートアップファイナンスの潮流として、最近「ファイナンスミックス」というキーワードをよく聞くようになりました。この言葉の提唱者の一人でもある若林さん、まずはこの概念について教えていただけますか?
若林:はい。「ファイナンスミックス」は、まだ正式なファイナンス用語とまでは言えませんが、これから市民権を得ていってほしい言葉です。
簡単に言うと、融資、出資、補助金など、様々な資金調達方法の特性を理解し、それらを組み合わせることで成長資金を確保していく、という考え方です。複数の手法をミックスして最大活用し、スタートアップがサバイブしていくための概念ですね。
もともとは、フェムトパートナーズの坂本さんというキャピタリストの方と「複数の資金調達方法を組み合わせる概念を提唱したいね」と話していた際に、坂本さんが「ファイナンスミックス」という言葉を提案され、それ以来使い続けています。
冨岡:なるほど、発信源は若林さんと坂本さんだったのですね。
村上さんも 著書『60分でわかる!ファイナンス超入門』の中でファイナンスミックスに触れられていますが、なぜ今このタイミングで注目されているのでしょうか?
村上:おそらく10年ほど前、2020年より手前では、「スタートアップのファイナンス=エクイティファイナンス」という概念が非常に強かったと思います。
中小企業が基本的に銀行借入であることや、上場企業が公募増資を滅多にしないことを考えると、スタートアップのエクイティ中心の資金調達は、実はかなり特殊な世界だったんです。
しかし近年、特に若林さんのご活躍もあって「ベンチャーデット」という、スタートアップ向けのデットファイナンスの認知が非常に高まってきました。それに伴い、金融機関もここ5年ほどで赤字のスタートアップにも融資を出すようになってきた。こうした背景から、エクイティとデットを統合し、全体最適を考える「ファイナンスミックス」がフィーチャーされるようになったのだと思います。
若林:まさにおっしゃる通りです。私も10年ほど前にスタートアップの融資支援を始めた頃、あるVCから紹介された訪問先で開口一番、「我々スタートアップだから融資なんて考えてないんです」と言われたことがあります。当時はそうした考えの会社が少なくありませんでした。
潮目が変わったのは、2021年頃にエクイティの市場環境が少しクラッシュしてからです。
シリーズA以降の調達が難しくなったり、長期化したりする中で、駆け込み寺的にデットファイナンスを使うケースが増えました。そこから、ようやく資金調達戦略の中にデットを本格的に組み込んで考えるスタートアップが増えてきたと感じています。
ただ、まだエクイティ一本足打法のスタートアップの方もいらっしゃいますし、逆にハイバリュエーションで調達した後にエクイティが入れにくくなり、デットを借りすぎて債務超過に陥ってしまった、というご相談も増えています。だからこそ、戦略的に最適なミックスを考える必要があるのです。
「ベンチャーデット」から「RBF」まで。多様化するデットファイナンスの世界
冨岡:エクイティ以外の選択肢としてデットファイナンスが重要ということですが、具体的にどのような手法があるのでしょうか。「ベンチャーデット」や「RBF」と言われても、ピンとこない方も多いかと思います。このあたりを若林さんに解説いただけますか?
若林:はい。まず、日本の創業融資制度は非常に優れていて、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資は、起業家なら誰もが一度は通る道になりつつあります。
その次のステップが、保証のつかない「プロパー融資」です。しかし、先行投資で赤字になりがちなスタートアップは、決算書の内容を重視されると審査が厳しくなります。この「死の谷」を越えるために出てきたのが「ベンチャーデット」です。
もともとは米国のシリコンバレーバンクが始めた手法で、デットファイナンスに新株予約権などのエクイティ性を組み合わせたものでした。最近では概念が広がり、エクイティ性が付かないものも含め、スタートアップ向けのデットファイナンス全般を指して使われることが増えています。
冨岡:プロパー融資と、エクイティ性のないベンチャーデットの違いはどこにあるのでしょうか?
若林:プロパー融資は主に銀行が提供する保証なしの融資です。一方、エクイティ性のないベンチャーデットは、ノンバンクが提供したり、銀行でもスタートアップ専門部署が通常より高い金利でリスクを取って提供したりするものをイメージしていただくと分かりやすいと思います。
村上:補足すると、銀行の審査基準は通常の融資とベンチャーデットで全く異なります。例えば、2期連続赤字の企業に通常の基準で融資を出すのは非常に難しい。しかし、一部のメガバンクでは、専門の部隊がスタートアップ向けの別の審査ロジックで評価を行っています。だからこそ、赤字でも融資が可能になるのです。
若林:こうした融資以外にも、新しい資金繰り支援サービスが増えています。例えば「RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンス)」は、将来の売上を早期に現金化するサービスで、SaaSのような将来の売上が見込みやすいビジネスモデルと相性が良いです。他にも、支払いを立て替えて分割払いにしてくれる「BNPL(Buy Now, Pay Later)」のようなサービスもあります。
これらを活用することで、成長機会を逃さずに次のエクイティやデットファイナンスへ繋ぐ「ブリッジ」として使うスタートアップが非常に増えていますね。

【事例から知る】タイミーはなぜ3年間で3桁億円のデット調達ができたのか?
冨岡:では、実際にこれらの手法をどのように「ミックス」していくのでしょうか。ステージごとに考え方があれば教えてください。
若林:あえて創業期とミドル・レイターステージに分けると、事業の不確実性が高い創業期は、創業融資を使いつつも、リスクマネーであるエクイティの比重が大きくなります。
一方、PMF(プロダクトマーケットフィット)を達成し、事業の不確実性が下がってきたミドル・レイター期には、資本コストが相対的に低いデットファイナンスを積極的に活用すべきです。これにより、希薄化を抑えながら成長資金を確保できます。このフェーズに応じたバランスを取ることが、ファイナンスミックスの肝です。
冨岡:具体的な事例として、タイミーさんの話をよく聞きます。
若林:タイミーさんは典型的な例ですね。創業者の小川さんは学生起業家で、当初はデットファイナンスのハードルが高かったと思われます。そこで初期はエクイティで事業を成長させ、事業規模が大きくなり、CFOの八木さんが参画されてから、一気にデットファイナンスに舵を切りました。2021年のエクイティ調達を最後に、上場までの約3年間はデットだけで3桁億円を調達し、事業を成長させたのです。
冨岡:3桁億円のデット調達は普通では考えられませんが、なぜ可能だったのでしょうか?
村上:それはタイミーさんのビジネスモデルの特殊性に理由があります。タイミーさんは求職者に給与を即日支払いますが、求人企業からのタイミーさんへの入金は翌月以降です。つまり、成長すればするほど、先に出ていくお金が増え、資金繰りが厳しくなる構造なのです。
これをエクイティで賄うと調達コストが高い上に、希薄化が非常に大きくなってしまう。
一方で、タイミーさんの貸借対照表(BS)を見ると、資産の多くを求人企業への「立替金」が占めています。金融機関からすれば、その裏には与信審査がしやすい大手企業などがいるため、非常に「堅い(かたい)」資産に見える。過去の貸し倒れ率も極めて低い。この点が、巨額のデット調達を可能にした最大の要因です。
若林:八木さんがCFOに就任された頃には、事業リスクはかなり低減されており、残っていたのは資金繰りのギャップだけでした。このギャップを埋めるためのファイナンスはリスクが低いため、低金利のデットで調達すべきだった、ということです。資本コストが年利20〜30%にも換算されるエクイティで調達すべきではなかったのです。
冨岡:なるほど。ビジネスモデルの特性を活かしたわけですね。この事例から他のスタートアップが学べることは何でしょうか?
村上:もう一つ重要なのは、CFOの八木さんが毎月のように複数の金融機関と対話し、予実管理の精度を見せ続け、信頼関係を構築したことです。これは簡単なことではありませんが、多くのスタートアップが真似できる部分だと思います。事業の状況を正しく説明し、納得してもらえれば、赤字であっても大型融資の可能性は十分にあるということです。
冨岡:タイミーさんの例は、アーリー期はエクイティ、ミドル以降はデットと、時間軸で使い分ける「ファイナンスミックス」の好例ですね。
村上:おっしゃる通りです。M&Aの際の買収ファイナンスなどは、エクイティとデットを同時に調達しますが、スタートアップの場合は成長フェーズという時間軸によって最適なミックスが変わってくるのが特徴です。この発想は、エクイティ中心のVC出身者や、デット中心の金融機関出身者だけでは生まれにくく、両方を理解しているからこそ生まれる新しい概念だと思います。
若林:時間軸だけでなく、同じラウンドの中でミックスする例もあります。例えば、家具のサブスクリプションサービスを提供しているクラスさんは、直近の調達でエクイティは一部に留め、残りをデットとセール・アンド・リースバックで調達しています。
冨岡:クラスさんの事例で、なぜ一部でもエクイティを入れることが重要だったのでしょうか?デットだけでも良かったのでは?
若林:もしデットだけで調達すると、負債の割合が大きくなりすぎて自己資本比率が下がり、会社の安定性を損なってしまいます。自己資本比率が下がりすぎると、「次の」デットファイナンスが非常に厳しくなってしまうのです。
そこで、エクイティを少し入れることで自己資本比率のバランスを保ち、次の調達余力を残しておく。これは非常に高度な戦略ですが、ファイナンスミックスの要点の一つです。
▼参考:Podcast クラスさんの総額25.3億円調達の「ハイブリッド・レバレッジ」解説回
ファイナンスミックスへの布石と、‘’手段‘’であるということ
冨岡:これからファイナンスミックスを検討する経営者は、何から始めればよいでしょうか?
村上:タイミーさん、クラスさん、そして素材開発のスパイバーさんなど、成功事例はそれぞれ全く異なる理由でデット調達を実現しています。これは、事業戦略と財務戦略が表裏一体だということです。自社の事業構造だからこそ使えるファイナンスの「工夫」があるはずです。
こうしたスキームは非常にクリエイティブで、金融機関や投資銀行出身者など、外部の専門家の知見を活用しながら作り上げていくのが良いでしょう。前例のない価値を提供するスタートアップにとって、ファイナンス面でも創造性を発揮できる部分は大きいと思います。
若林:私が皆さんにお伝えしたいのは、「できるだけ早い段階で創業融資などを活用し、借入の返済実績を作ってください」ということです。デットファイナンスは、返済を積み重ねてレベルを上げていくゲームのような側面があります。早くゲームを始めれば、それだけ有利になります。これが将来のファイナンスミックスに繋がっていくのです。
冨岡:私も、特に1周目の起業家の方には「まず日本政策金融公庫から借りる。エクイティを入れるならエンジェル投資家から普通株で」というのがデフォルトの動き方だと考えています。M&Aを考えるならなおさら、安易に優先株で調達すべきではないですよね?。
若林:全く同意見です。ただし、例外として、VCバックで急成長を目指すべき巨大市場を狙うスタートアップは、最初から優先株で調達する方が良いケースもごく一部にはあります。
村上:何より重要なのは、資金を使って仮説検証をしっかり行うことです。例えば創業融資で1,000万円を借りても、顧客の課題を捉えられていなければ、次のVCからの調達には繋がりません。資金調達はあくまで手段であり、事業を前進させることが本質です。そこを意識してほしいですね。
本日の学び
- ファイナンスミックスは「融資+出資+補助金など・・」を組み合わせ、成長資金を戦略的に確保する考え方
- エクイティ一本足ではなく、デットや多様化する資金繰り手法(RBF・BNPLなど)を取り入れることで選択肢が広がる
- デットファイナンスは、借入実績をつくることが重要。早い段階で創業融資など活用することで、将来のファイナンスミックスにつながっていく
- 大前提、資金調達は目的ではなく、仮説検証と事業成長を前進させる手段でこと念頭に