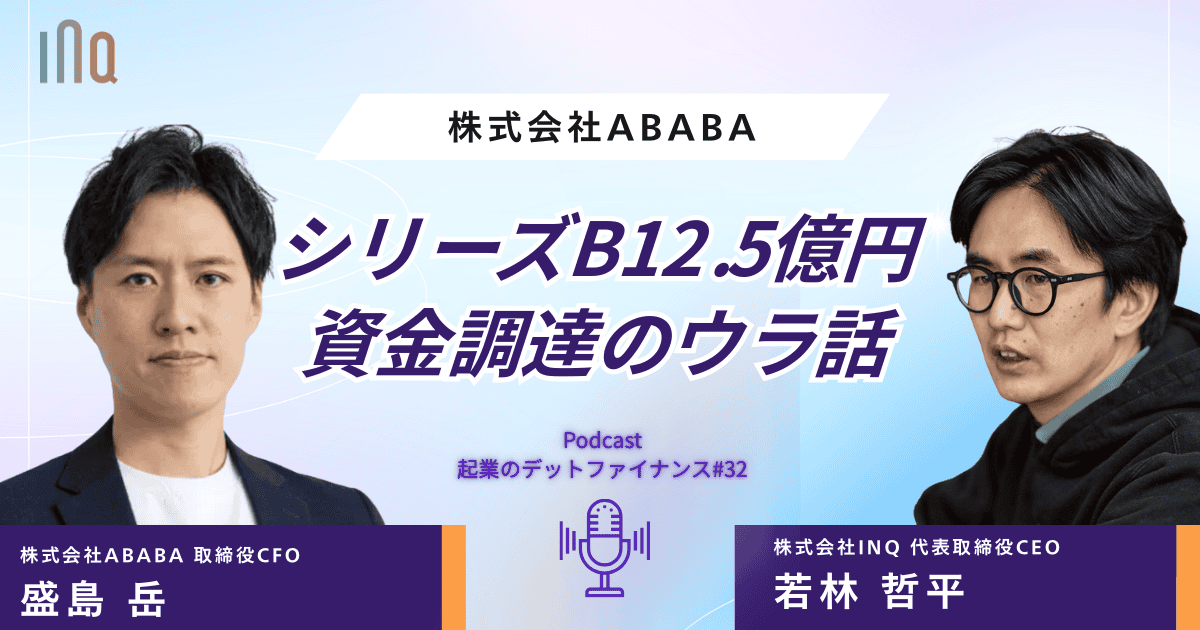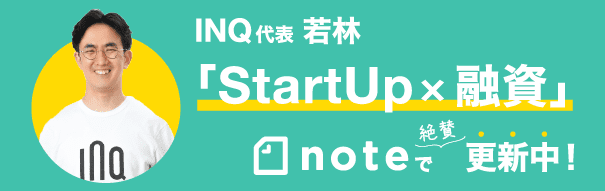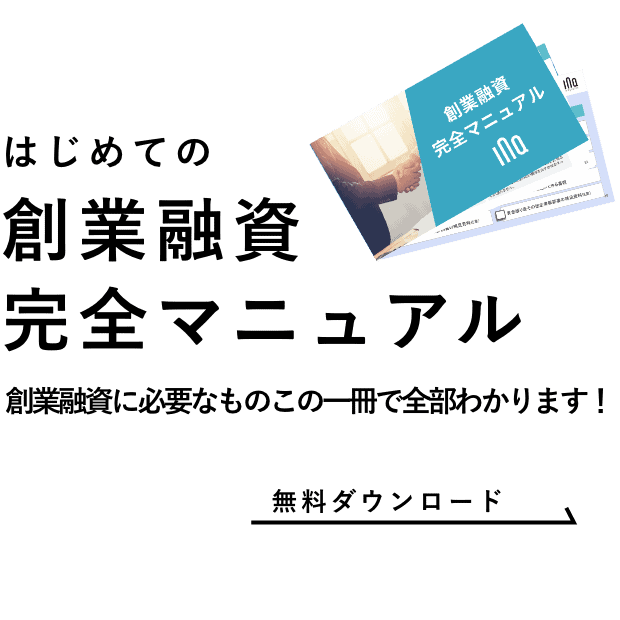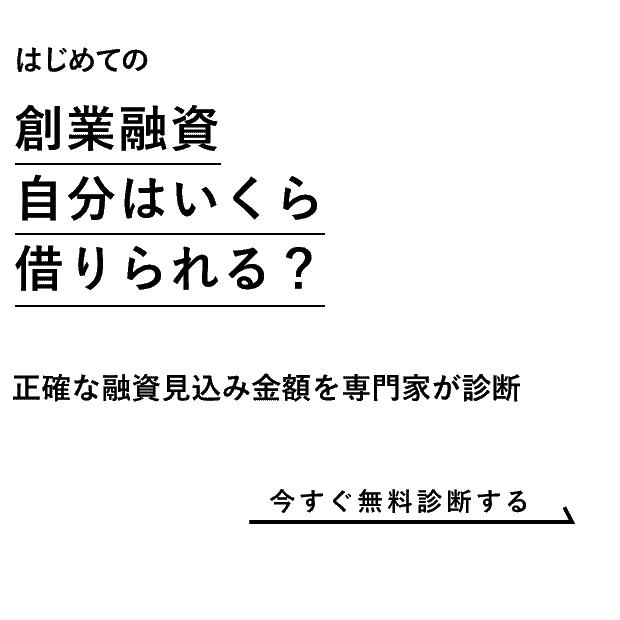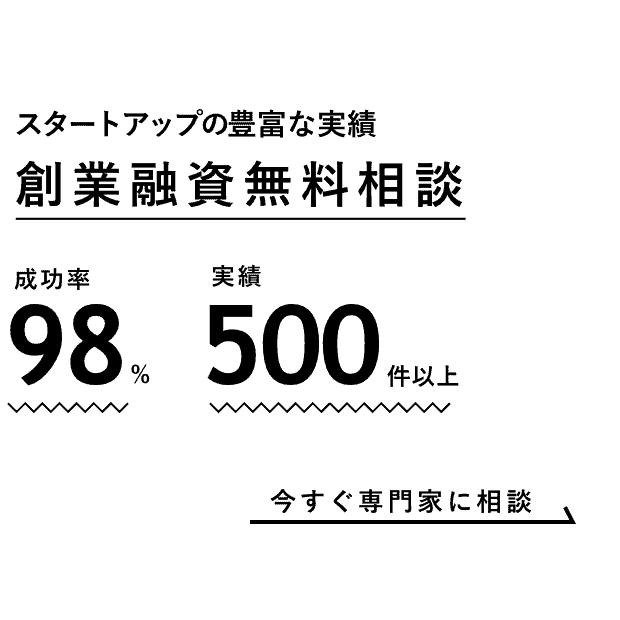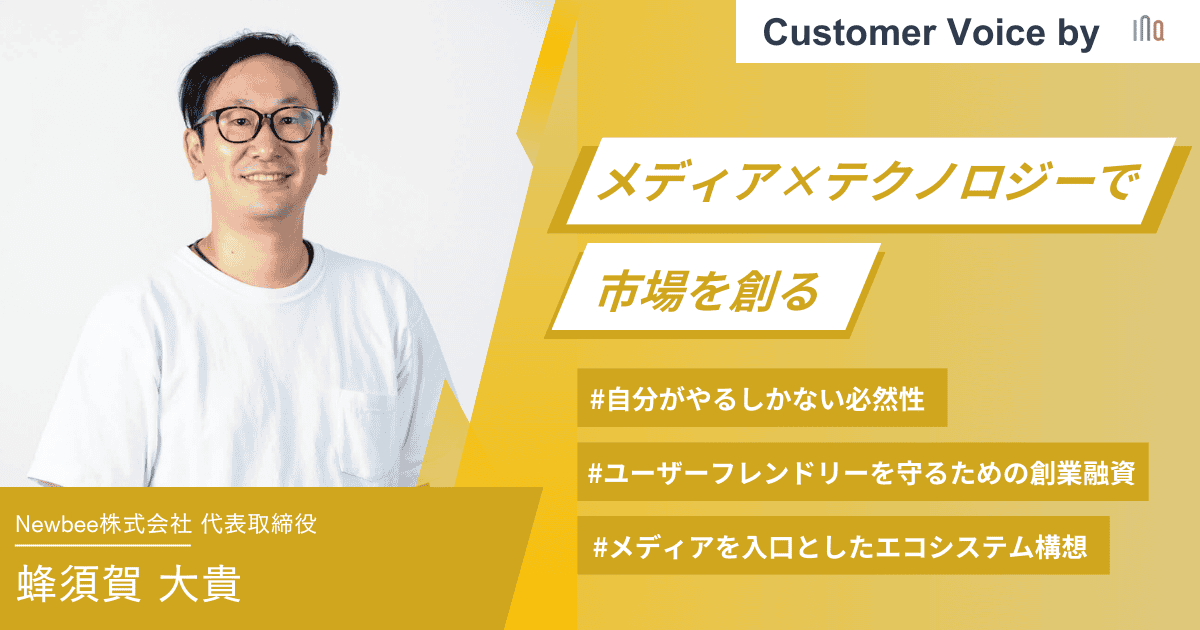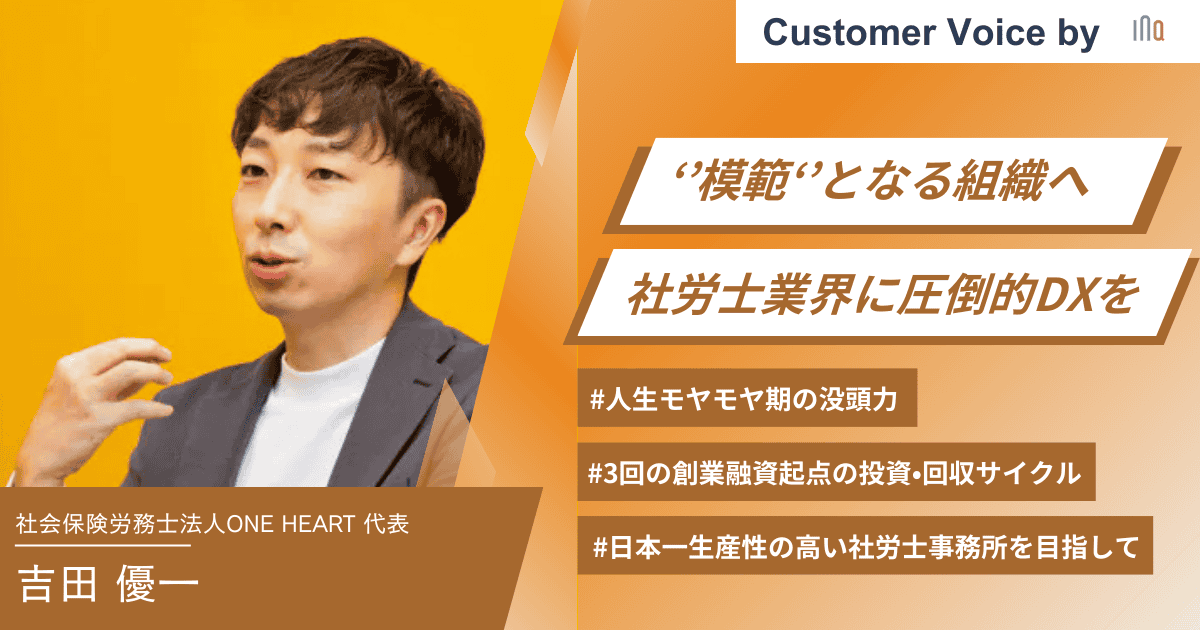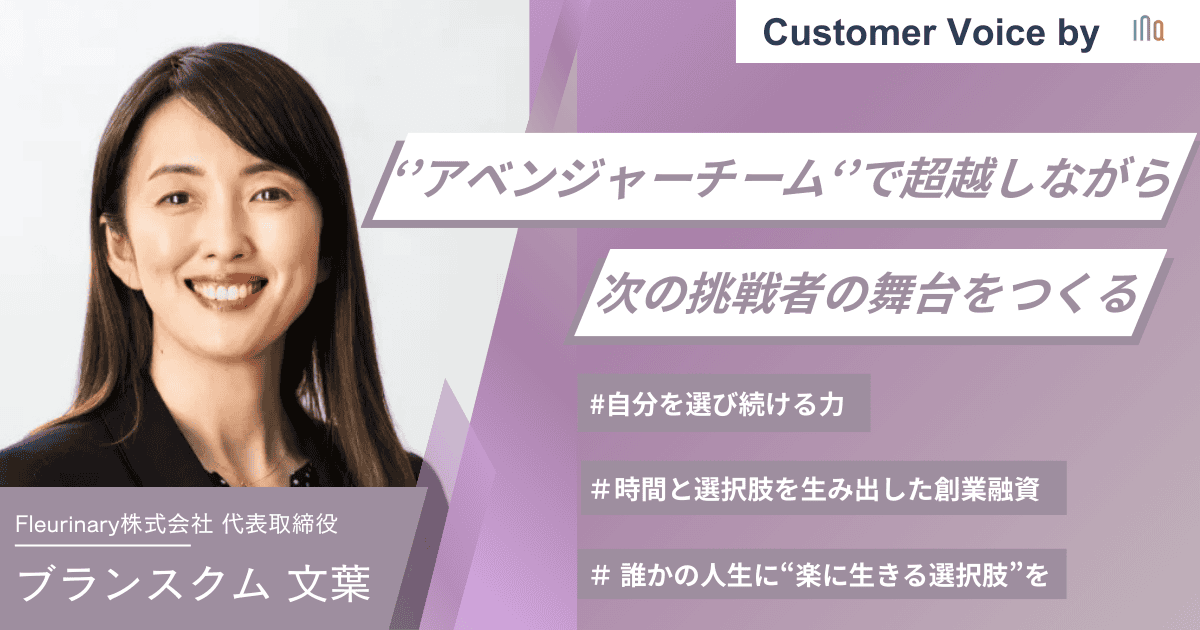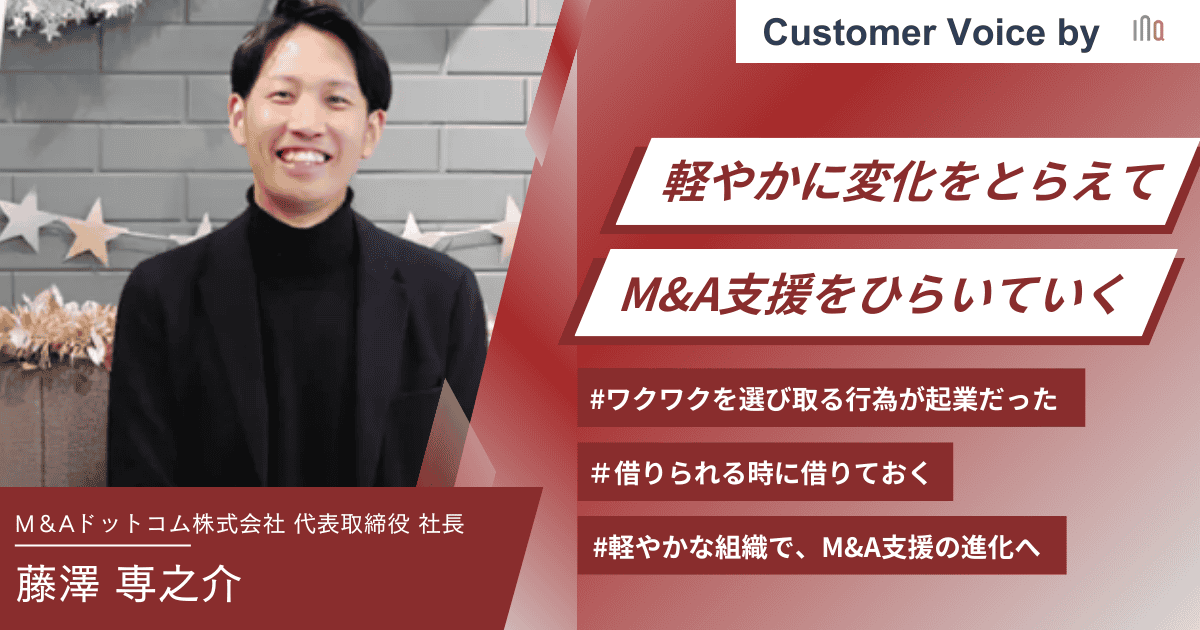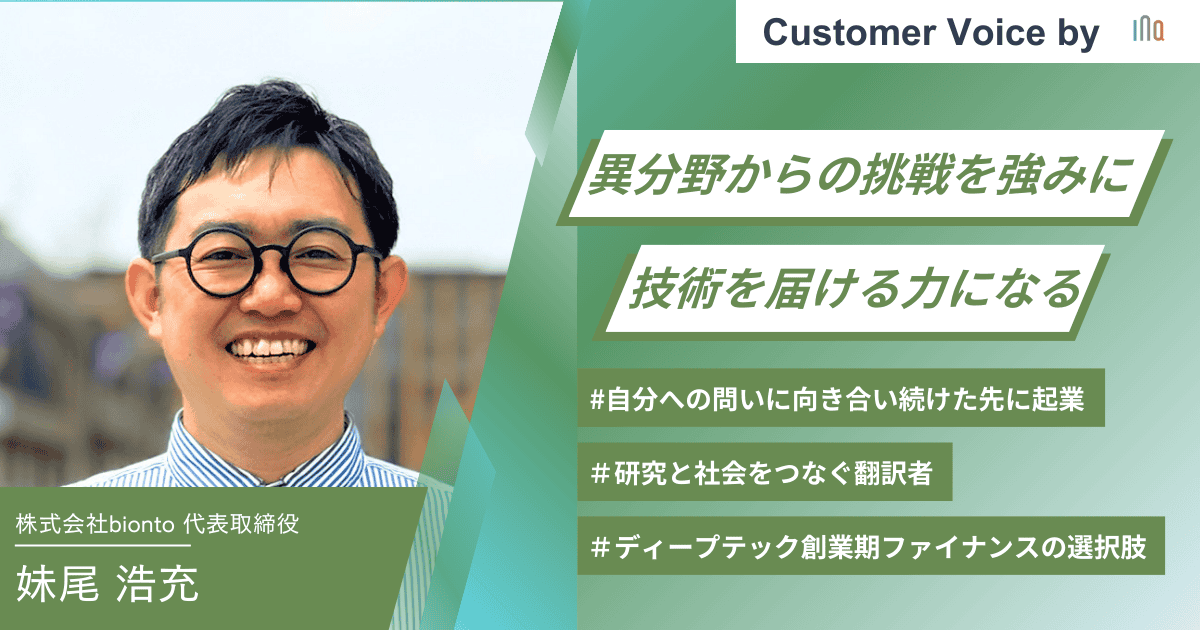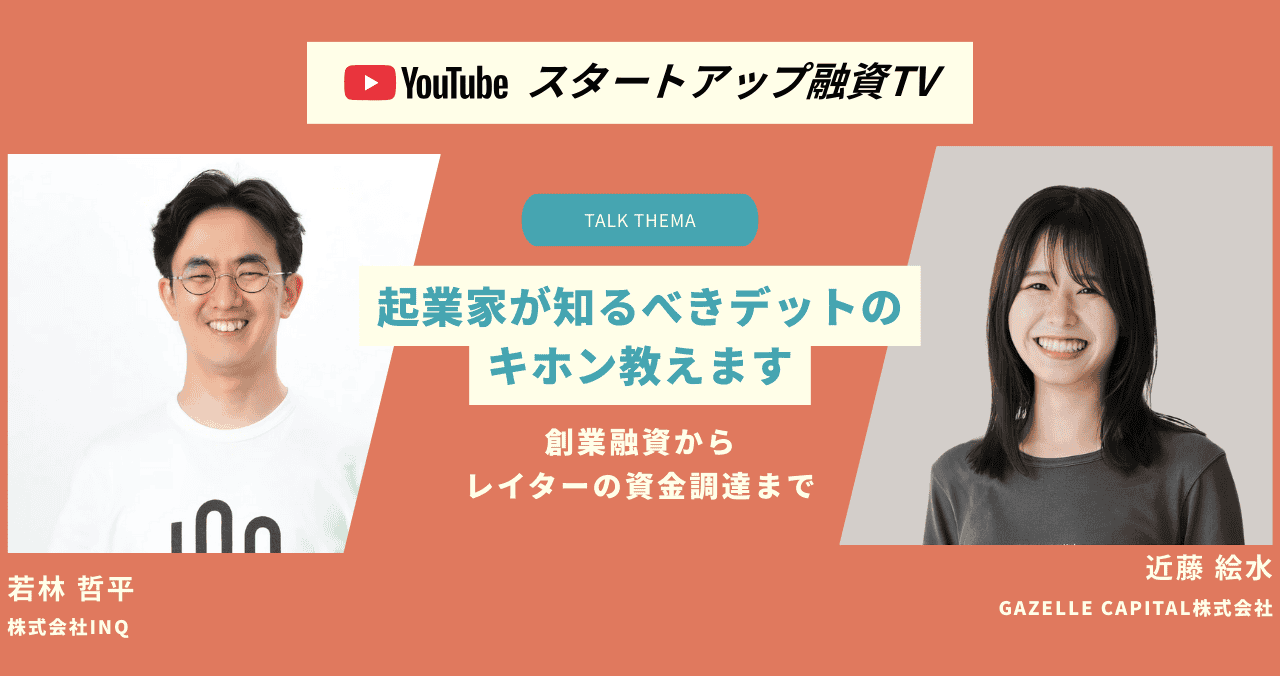若林 哲平
最新記事 by 若林 哲平 (全て見る)
- 【融資相談室】知らないと損!無担保・無保証の「女性・若者・シニア創業サポート事業2.0」を徹底解説 - 2025年12月12日
- 【M&Aバンク】押さえておきたい実践の視点|ファイナンスミックスをどう始める? - 2025年9月30日
- 【融資相談室】日本政策金融公庫 資本性ローンで5000万円を掴む!融資のプロが語る「攻めの調達戦略」 - 2025年9月25日
年間500名以上の起業家から資金調達の相談を受けるINQの若林が運営する番組「起業のデットファイナンス」に株式会社ABABA 取締役 CFO盛島さんにご出演いただきました。今回は2025年4月9日・15日配信の「ABABAシリーズB12.5億円 資金調達のウラ話 前編 / 後編」内容を記事化しましたので、ご覧ください。
▼出演者プロフィール:
株式会社ABABA 取締役 CFO 盛島 岳
同志社大学経済学部卒業。公認会計士。大学卒業後、有限責任監査法人トーマツに入所。事業会社及び金融機関の財務諸表監査や内部統制監査等に従事。その後アドバイザリー部門に異動し、企業価値評価・財務デューデリジェンス等のFAS業務や、会計助言、業務プロセス構築、経営管理高度化、PMI、PMO等、幅広い領域でのアドバイザリー業務に従事。
「お祈りメール」からの逆転。次のチャンスを生む構造へ
若林:
まず、貴社の事業概要についてお伺いできますか?
盛島:
株式会社ABABAは、新卒採用支援を行うスタートアップで、設立5期目を迎えています。
主力サービス「ABABA」は、最終面接まで進んだ就活生が登録し、就活プロセスを評価した企業からスカウトを受け取れるという仕組みです。これまで“お祈りメール”で終わっていた就活プロセスに、新たなチャンスを生む構造をつくり、学生・企業双方に大きな価値を提供しています。
若林:
就活の最後である「お祈りメール」からの逆転、そして起点となる自己分析や価値観の可視化という両面からアプローチしているのが面白いですね。
盛島:
まさに、就活の「ゆりかごから墓場まで」を支えるサービスと言えるかもしれません。
自己理解を深め初期的に企業接点が持てる入口として「REALME」そして最終面接まで進んだ就活後半期でさらに選考機会が得られる出口として「ABABA」を活用いただくことで、より良いキャリア形成を支援したいと考えています。
企業にとっては、他社で最終面接まで進んだ優秀な学生に的を絞ってアプローチでき、選考の一部を短縮できるというメリットがあります。学生にとっては、努力の過程が「評価対象」となり、従来は実質的に無価値だった就活プロセスが価値化されることでそれまでの経験が次のチャンスにつながります。
おかげさまで、サービス開始から4年で累計利用企業は2,000社を超え、これまでの利用学生数は累計10万人に到達しました。
この「ABABA」は、弊社共同代表の久保と中井が学生時代に立ち上げたもので、最終面接で不採用になった友人の悔しさをきっかけに「この社会構造を変えたい」と思ったことが原点です。
加えて新サービス「REALME」では、AI面接により学生の価値観やスキルを可視化し、企業の採用要件と照らし合わせることで、より早い段階からの高い精度でのマッチングを可能にしています。
就活を「全国共通模試」のように捉え、自分の立ち位置や改善点をAI面接でのフィードバックを通じて知ることで、安心感を持ちながら前に進める仕組みを提供しています。
資金調達の変遷とその背景
盛島:
最初のファイナンスは2020年2月、シードラウンドで、ウィルグループさんやSetouchi Startupsさん、複数のエンジェル投資家から約6,000万円を調達しました。その後、プレシリーズAでDeNA南場会長率いるデライト・ベンチャーズさんはじめとするVC数社から1.2億円、シリーズAラウンドでは3.7億円を調達しています。
シリーズA以降はリード投資家のNESさん、SMBCベンチャーキャピタルさんや三菱UFJキャピタルさん、ちゅうぎんキャピタルパートナーズさんなどもご参画いただきました。2025年3月のシリーズBでは、DBJキャピタルさんがリードとなり、JPインベストメントさんや、既存投資家にも引き続きご支援いただいています。
若林:
すごい顔ぶれですね。これらのラウンドで調達された資金の使途について教えてください。
盛島:
弊社は新卒採用支援というビジネス特性上、売上が出るのは内定が出るタイミングです。
つまり、学生が3年生のときから接点をつくり、4年生で内定が出て承諾されると弊社の成果報酬が発生します。ですので、先に投資して後から回収するというビジネスモデルになっています。
若林:
いわゆるキャッシュ・コンバージョン・サイクルが長いモデルですね。資金繰りが重要になると。
盛島:
まさにおっしゃる通りです。ですから、事業の成長を止めないために、資金繰りの部分はデットファイナンスでしっかりと埋め、成長投資の部分はエクイティでというふうに明確に分けて資金調達を行ってきました。
若林:
資金の「色」を意識して説明されていたわけですね。
シリーズBラウンド:新規事業投資への意思決定となった明確な基準
若林:
今回のシリーズBラウンドにおいて、特に難しかったことやCFOとしてきつかった局面を教えてもらえますか?
盛島:
最もタフだったのは資金調達プロセスに入る前段階において「新規事業への投資を進めるかどうか」の意思決定でした。
既存事業「ABABA」が順調に伸びていたこともあり、新サービス「REALME」にリソースを割かずに「既存事業に集中するという意見も挙がりました。」い
若林:
そうした声に、どのように対応されたのでしょうか?
盛島:
熱意だけでなく、数字に基づくシミュレーションを徹底的に行いました。
投資金額、損益影響、資金繰り、次回のファイナンススケジュール、さらには撤退基準まで、すべてを可視化し、共有しました。「このラインを超えなければ見直す」といった明確な線引きを行うことで、共通認識が持てたと思います。
若林:
数字で語ることで、空中戦にならず納得を得られたのですね。
盛島:
結果的に、そういった丁寧なプロセスがシリーズBの資金調達に非常に活きました。
既存事業で見えてきた成長性と、新規事業の可能性についても徹底的に議論を重ねたうえで、しっかりと準備して臨めたことが大きかったと思います。
正直、タフな局面も多かったですが、今振り返ると「考えるべきことにしっかり向き合えた時間だった」と思っています。
若林:
投資家からのDD(デューデリジェンス)も、かなり厳しかったのではと感じました。そうした厳しいプロセスの中で得られた気づきについてはいかがでしょうか?
盛島:
今回の調達プロセスでは、本当に多くの投資家の皆さまからさまざまなご意見を頂きました。その中で、私たち自身が持てていなかった視点や、より深く考えるべきポイントに気づかせていただきました。
やはり、いろいろな方と対話を重ねること自体が、とてもありがたい機会だったと感じています。
そうした継続的な対話やその積み重ねが結果的に信頼に繋がり、比較的スムーズなシリーズBクローズに結びついたと思います。
若林:
既存の投資家様からのフォローオン出資がスムーズだった背景には、どのような工夫があったのでしょう?
盛島:
弊社では、株主の皆さまに対して毎月、月次報告会を実施しています。損益やトピックス、新規取り組みについても継続的に共有しているため、「調達のときだけ連絡する」という関係ではありませんでした。
また、金融機関にもニュースや簡単な進捗レポートを随時共有しており、結果として信頼関係が醸成され、スムーズな融資実行にもつながったと考えています。
IPOを見据えた資金構成(デット・エクイティとの整合性)
若林:
シリーズBラウンドでの資金構成の考え方やIPOを見据えた意図など、もう少し詳しく教えてください。
盛島:
弊社では「将来的にIPO後も時価総額を上げ続けられる企業でありたい」という思いがあります。そのため、IPO時点で一定の経営権を保有し続けることを重視し、希薄化をなるべく避けるようにしています。結果的に、アーリーステージとしては比較的デットを多めに活用している方だと思います。
最近はよりスケールする企業に資本が集中する傾向を感じています。だからこそ、我々も機会損失を防ぐために、ある程度のリスクをとってでもデットを活用し、事業を成長させるスタンスを取っています。
若林:
直近、グロース市場の上場維持基準が時価総額100億円以上に変更となるという速報ニュースも出ていましたが、率直にどのように捉えられていますか?
盛島:
弊社としては、ポジティブに受け止めています。もともと「100億円の時価総額で上場を目指す」というより、将来的に1兆円企業を目指したいという思想があるので、影響はほとんどありません。
むしろ、社会的リソースや投資家様の目線がより「本気でスケールする企業」に向くことで、証券会社や監査法人が集中しやすくなり、社会全体としても健全になると感じています。ですので、制度改正自体はポジティブに捉えています。
VCや金融機関とのコミュニケーション
若林:
素晴らしいです。
資金供給プレーヤーの方とのコミュニケーションも丁寧にされていた印象ですが、その点はいかがでしょうか?
盛島:
特に「将来、より大きな借入を実現するためには、早期から関係性を築いておくことが不可欠」だと考え、シリーズBの時点でいくつかの銀行様としっかり向き合う時間を設けました。
また、金融機関だけでなくVC様に対しても、「使いやすい資料」を心がけました。
たとえば、IR資料に近いフォーマットで、業界の構造・ポジショニング・戦略・財務などを一連の流れで説明できる資料を用意しました。VC様がそのまま社内の投資委員会にかけられるような内容にすることで、スムーズな意思決定を後押しできたと思います。
若林:
デットとエクイティの整合という意味では、どのような整理をされたのですか?
盛島:
資金用途(資金使途)ごとに色分けをしていました。
運転資金や既存事業の拡大にはデット、新規事業や研究開発などリスクが高い領域にはエクイティ。また、保守的な「ネガティブプラン」と成長性を見込んだ「ベースプラン」と、事業計画も2種類用意して説明していました。
戦略的デットファイナンスの活用と合意形成プロセス
若林:
今回のシリーズBにおけるデットファイナンスには、他にも戦略的な意図があったのでしょうか?
盛島:
大きな狙いの一つは、「将来的により大きな借入を実行する際に、すでに信頼関係のある金融機関がある」状態をつくっておくことでした。
金利が多少高くても、今の段階で関係性を築いておくことが、次のラウンドでの融資や相談のしやすさにつながると考えました。
加えて、事業が前年比8〜9倍で伸びていたこともあり、資本コストの観点からもデットのほうが有利という判断でした。また金融機関からのピッチイベントへのご招待や営業先のご紹介など、副次的な恩恵も多く、ファイナンス手段として非常に良い選択だったと感じています。
若林:
デットファイナンスを進めるにあたり、どのようなコミュニケーションが効果的だったと感じますか?
盛島:
重視したのは「実績の再現性」です。
売上やKPIの推移を丁寧に説明し、「この構造なら今後もキャッシュが積み上がる」という信頼を積み上げました。担当者の方とは何度もZoomや電話でやりとりし、事業への深い共感のもと「この案件を通したい」と言っていただけたのはありがたかったです。
若林:
一方で、エクイティとの整合も重要だったと思います。社内での議論はどう進められたのでしょうか?
盛島:
経営陣の共通認識として、「成長を止めたくない」という想いがありました。
だからこそ、シリーズA直後の段階でたとえばエクステンションラウンドなどでエクイティで調達すれば希薄化リスクが高くなるため、まずはデットでランウェイを確保し、バリュエーションが上がってからエクイティに進もうと提案しました。シナリオとリスクを整理して説明したことで、合意形成が進んだと感じています。
若林:
KPIの見せ方についても工夫があったそうですね?
盛島:
単に「売上」ではなく、たとえば「スカウト数→面談→内定→成果報酬」というフローを指標ごとに分解して説明しました。また、単価×成約数というP/L構造と、「この指標が伸びれば何か月後に売上に反映される」という再現性のあるストーリーを提示しました。
また、業界平均や他社と比較することで、「評価の物差し」を示すようにしました。
弊社のように先行指標と変数が多いビジネスモデルですと評価基準が曖昧なので、「このKPIが業界平均より優れている」「他社と比較して成果が出ている」といった説明は、資金供給側の理解促進に繋がったと思います。
若林:
決算や金融機関との関係づくりの視点で意識されたことはありますか?
盛島:
金融機関は決算書の更新タイミングを重要視する傾向があります。
ただ、スタートアップの場合は先行投資が多く、数字だけでは判断が難しい場面もあります。
私たちは、決算そのものを調整するのではなく、数字の文脈を丁寧に説明することに注力しました。たとえば「このコストは来期には発生しない挑戦的な投資です」と伝えることで、決算情報だけでは見えてこない真の収益力について理解を得るよう努めました。
CFOとして、よき理解者を増やしていく動きの重要性
若林:
改めて、今回のファイナンスの進行において、印象的だった場面を挙げるとすれば?
盛島:
金融機関のご担当者が前向きでも、行内稟議の過程で種々の事情でストップがかかったりですとか、事業計画と実績の整合性検証に時間を要することもあります。
だからこそ、「どの状態になれば融資いただけるのか」を早い段階から会話するようにしていました。こちらから逆算してP/L・B/Sを設計するための材料になりますし、信頼関係の土台づくりにもなります。
よって、調達前から動かないと間に合わない前提はあるものの、例えばマーケティングや開発は、リリースの数ヶ月前から投資が始まるのでまだ資金が確定していない状態で、先にお金を出すと意思決定し、調達に動く、実行するというのは、正直ヒリつく感覚もありました。
もちろん、ベスト・ベース・ワーストのシナリオは用意していましたが、「走りながらファイナンスを通す」というのは、CFOとしての胆力が試される場面でもありました。
若林:
なるほど。
最後に、今回のファイナンスをご経験された上で、他のCFOの方へお伝えできる気づきがあれば教えてください。
盛島:
「ファイナンスが決まってから動く」のでは遅いということ。
決まる前から走り始める必要がある。
そのような矛盾のプロセスの中でも、数字・熱意・計画をしっかり整えてお伝えしていけば、きっと理解者は現れると思います。
改めて、弊社は「隣人を助ける」というカルチャーを大切にしています。
今回のファイナンスを経て、既存サービスの磨き込みに加え、新規事業にも積極的に挑戦していく予定です。
学生や企業人事の方にとって「出会えてよかった」と思えるサービスを届けることが、学生や企業の可能性を最大化させ、ひいては国力の向上にもつながると信じて、今後も事業に向き合っていければと思います。
*
▼就職活動の過程が評価される 「ABABA」サービス
https://hr.ababa.co.jp/
▼ ABABA|絶賛採用強化中
https://hr.ababa.co.jp/ababa#career
▼ ABABA|広報NOTE
https://note.com/ababa_koho
*
▼本記事のポッドキャスト配信